Site Calendar
NAVI
ログイン
記事カテゴリ
新着情報
記事
-コメント (2日)
-トラックバック (2日)
-リンク (2週)
新しいリンクはありませんQRコード
アンケート
三国志ニュースのレポート系記事
他のアンケートを見る | 84 投票 | 0 コメント
メモ:踞牀
- 2007年1月17日(水) 23:30 JST
-
- 投稿者:
- 清岡美津夫
-
- 閲覧数
- 18,077

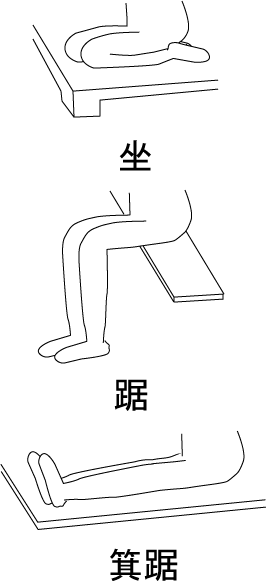 ※随分前に書きかけで放置していたのをちょっとつけ足してアップしました。放置するとそのまま日の目をみない恐れがありましたので。
※随分前に書きかけで放置していたのをちょっとつけ足してアップしました。放置するとそのまま日の目をみない恐れがありましたので。2006年11月10日に発売した文庫の「十八史略 2 権力の構図」を読んでいると、自分が肝心なエピソードを忘れていたことに気付く。ちょうど漢朝のできる前のところ。劉邦関連のエピソードのところだ。
・史記卷八 高祖本紀第八
[麗β]食其(謂)〔為〕監門、曰:「諸將過此者多、吾視沛公大人長者。」乃求見説沛公。沛公方踞牀、使兩女子洗足。[麗β]生不拜、長揖、曰:「足下必欲誅無道秦、不宜踞見長者。」於是沛公起、攝衣謝之、延上坐。食其説沛公襲陳留、得秦積粟。
※史記[麗β]食其伝では「沛公方倨牀」となっている
訳は略すんだけど、このエピソードは[麗β]食其が沛公(漢の高祖、劉邦)に面会した際、沛公が牀の縁に踞し足を二人の女子に洗わせていたというもの。
<2007年11月16日追記>
「不拜、長揖」については下記記事参照
・三国創作のための拝メモ
http://cte.main.jp/newsch/article.php/736
<追記終了>
このエピソードのことをすっかり忘れていたんだけど、ここで私が注目したのは「沛公方踞牀」のところ。字通CD-ROM版で調べると「踞」とは腰をかけてすわる意味らしい。ちょうど右の図のようになるかな。
つまり沛公は牀に腰掛けていたとのこと。「牀」に関してはここ三国志ニュースで過去、何度か取り上げているので、そちらの記事(下記の三つ)を参照のこと。
・「牀」 三国志の筑摩訳本を読む
http://cte.main.jp/newsch/article.php/221
・牀や榻のことばかり
http://cte.main.jp/newsch/article.php/286
・跪坐と垂足坐
http://cte.main.jp/newsch/article.php/344
三つ目の記事で書いていた「垂足坐」は当時の言葉でいうと「踞」となるんだね(「漢代物質文化資料図説」とエピソードを合わせると沛公の無礼さがどれぐらいかを伺い知ることができる)。
この「踞」は前々から私が知りたかった言葉だ。言葉をしっておくと電子テキスト内を検索するときに便利なものとなる。例えば椅子なんてない当時、実際、一般的には「踞」なんて座り方がどういったシチュエーションで行われていたか調べることができる。
今、さらっと三国志およびその注から「踞」で検索をかける
・三國志卷十六 魏書十六 任蘇杜鄭倉傳第十六
帝大怒、踞胡牀拔刀、悉收督吏、將斬之。
こちらは「牀」ではなく「胡牀」(胡床)。踞すことができる椅子に近い座具だったのかな。
※参照
http://cte.main.jp/c-board.cgi?cmd=one&no=532
・三國志卷五 魏書五 后妃傳第五の注に引く魏略
後太祖就見之、夫人方織、外人傳云「公至」、夫人踞機如故。
機織り器にも踞す。ここらへん画像石などに描かれている様と一致する。
あと「箕踞」という座り方。「箕」単体だとちりとりの意味で、総じて図のような座り方となる(例によって字通CD-ROM版を引いている)。エピソードの例としては下記のとおり。先主(劉備)の前でも箕踞している簡雍の様子が有名かな。
・三國志卷三十八 蜀書八 許麋孫簡伊秦傳第八
在先主坐席、猶箕踞傾倚、威儀不肅、自縱適
<1月19日追記>
『中国社会風俗史』東洋文庫151を読んでいると、腰掛けて座るのは「據」ともいるらしい。用例は『世説新語』に多いとのこと。
確かに検索かけてみると『世説新語』にやたら「據胡牀」って言葉がひっかかる。
<10月13日追記>
『礼記』曲礼上第一に「坐毋箕」とある
※追記 『イナズマイレブンGO クロノ・ストーン』で劉備登場(2012年10月3日)
※追記 京都祇園祭後祭山鉾巡行で後漢関連(2016年7月24日)
※新規関連記事 図録 三国志(2019年6月19日)
※新規関連記事 メモ:兵馬俑と古代中国(京都市京セラ美術館2022年3月25日-5月22日)
トラックバック
- このエントリのトラックバックURL:
- http://cte.main.jp/newsch/trackback.php/485
この記事にはトラックバック・コメントがありません。

サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。