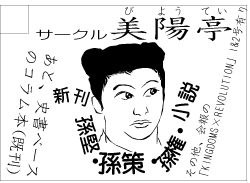小説の同人誌「単身帰還」の原稿書きに詰まってきたので、気分転換に「孫氏からみた三国志」の更新すすめる。元ネタは三国志からなので、手元のちくま訳を参考にちょちょいのちょい(死語)なんておもっていたが、どうもちくま訳に納得できず(該当する場所は文としてはすらすら読めるんだけど、素人目に漢文とどう対応するのかわからない)、かといって自分ではちゃんと訳せなかったので、うんうんうなっていた……結局、中途半端な文の理解になったんだけど(汗)。あとこのエピソードって孫堅とばしすぎだよね。董卓を斬れだなんて。後世の後付エピソードっぽくみえなくもない(汗)。まぁ、似たような例は孫堅が故事をあげているようにいろいろあるんだけどね。>>「斬司徒、天下乃安。」とか。もう一つ載せたのは、サークル「美陽亭」の名前の由来になった文台さんエピソード(>>由来)。あれって出来事だけ抽出すると、あんな短いことになるんやね(汗)。書き終えた後で思ったんだけど、美陽亭の北で文台さんが「殆死」(瀕死)になったんだったら、復帰するのに結構、期間の要ることだから、戦の終わり頃にあのエピソードが入るのが自然かなぁ。
小説の同人誌「単身帰還」の原稿書きに詰まってきたので、気分転換に「孫氏からみた三国志」の更新すすめる。元ネタは三国志からなので、手元のちくま訳を参考にちょちょいのちょい(死語)なんておもっていたが、どうもちくま訳に納得できず(該当する場所は文としてはすらすら読めるんだけど、素人目に漢文とどう対応するのかわからない)、かといって自分ではちゃんと訳せなかったので、うんうんうなっていた……結局、中途半端な文の理解になったんだけど(汗)。あとこのエピソードって孫堅とばしすぎだよね。董卓を斬れだなんて。後世の後付エピソードっぽくみえなくもない(汗)。まぁ、似たような例は孫堅が故事をあげているようにいろいろあるんだけどね。>>「斬司徒、天下乃安。」とか。もう一つ載せたのは、サークル「美陽亭」の名前の由来になった文台さんエピソード(>>由来)。あれって出来事だけ抽出すると、あんな短いことになるんやね(汗)。書き終えた後で思ったんだけど、美陽亭の北で文台さんが「殆死」(瀕死)になったんだったら、復帰するのに結構、期間の要ることだから、戦の終わり頃にあのエピソードが入るのが自然かなぁ。
そろそろ掃除はじめなアカンなぁとおもいつつ、小説書きかサイトの更新か読書にうつつを抜かしている。毎年、この時期に恒例になりつつある「ローマ人の物語」読んでいる、年に一回の刊行だから。あ、新刊は塩野七生/著「ローマ人の物語XIII 最後の努力」ね。まだ初めの方。あとは七年ぶりの新刊の、美内すずえ/著「ガラスの仮面」42巻。こちらは漫画とあって買ってすぐ読む。登場人物のファッションが現代っぽくなったっていっても表現方法は伝統的で安心(?)だね。あの白目になるところとか(笑)。もうすっかり話の流れを忘れているんだけど、恋の話がメインになって、紅天女の話がサブになっているような気がする。。。うーん、斜に見過ぎか。。。
来年はめずらしく初詣に行く予定だけど、「連続初詣」なるバカ企画(すでにタイトルの時点で矛盾が。。。)を考えてる。
最近、気になる三国志系サイトがある。知識系のサイト。何が気になるかっていうとサイト名で「正史三国志」系をうたっていて(しかし「正史」という単語の呪文はそんなに効果的と思われているのかね)、「三国演義」と明確な区別をしている風であるんだけど、どうも「三国志」や「三国演義」や周辺の書物を確認しつつコンテンツを書いておらず肝心なところが記憶に頼っているような内容なんで、誤認の内容(主に歴史とうたっていながら「三国演義」から引用されるってパターン)が多くすごく目に付く。いや、だから腹立たしいとかじゃなく、むしろ怖いもの見たさで楽しんでいるというか……(すみません、よく考えたら悪趣味・汗)。「わぁ」「あちゃー」「これは初心者が知った気になって誤解する!」とかつぶやきながら。でも突っ込もうにも掲示板がないんですよ、奥さん!(あったとしてもつっこみどころが多すぎて角が立つだろうな)。かといってメールで告げる気力もない。そのところどころの誤認さえ無ければ、初心者にお勧めできる姿勢のサイトなんだけど残念(…って応援する気は少しはあるんだね、私)。あと話が代わるんだけど、大陸では狭い意味での「三国志」を「三国歴史」(「歴」は簡体字)っていうの?

 関係ないけど、神戸ルミナリエに行ってくる。写真のような支持ケーブルか電源ケーブルによってあの明るさは支えられて居るんだなぁ、と。ちなみに上から群衆の方へ目を転じるとカメラ付き携帯の液晶画面が連なっている。これはこれである意味、アート。
関係ないけど、神戸ルミナリエに行ってくる。写真のような支持ケーブルか電源ケーブルによってあの明るさは支えられて居るんだなぁ、と。ちなみに上から群衆の方へ目を転じるとカメラ付き携帯の液晶画面が連なっている。これはこれである意味、アート。 2005,1/9 COMIC CITY 大阪52 歴史・古典ジャンル、三国志
2005,1/9 COMIC CITY 大阪52 歴史・古典ジャンル、三国志