ここ数年(光和年間)、前々回では南の辺境、三回前は北の辺境での乱にふれて、触れてないまでも他にも異民族の反乱などがあったが、幸いなことに、中央の部分では反乱が起こっていなかった。孫堅(字、文台)と呉夫人、息子二人に娘一人の家族が住むところもしかり。
ところが中央で反乱の影が忍び寄ることになる。
(というわけで、下
 住まいの孫さん一家は、しばらく出ません。失礼。それだけ見たい人は>>こちら)
住まいの孫さん一家は、しばらく出ません。失礼。それだけ見たい人は>>こちら)| << |
| 陰謀発覚!(孫氏からみた三国志15) |
031003
|
|
<<孫氏三代、揃う(孫氏からみた三国志14) ここ数年(光和年間)、前々回では南の辺境、三回前は北の辺境での乱にふれて、触れてないまでも他にも異民族の反乱などがあったが、幸いなことに、中央の部分では反乱が起こっていなかった。孫堅(字、文台)と呉夫人、息子二人に娘一人の家族が住むところもしかり。 ところが中央で反乱の影が忍び寄ることになる。 (というわけで、下  住まいの孫さん一家は、しばらく出ません。失礼。それだけ見たい人は>>こちら) 住まいの孫さん一家は、しばらく出ません。失礼。それだけ見たい人は>>こちら) |
|
えーと、後付かどうかは知らないけど、これから先の出来事を暗示する天文現象が起こる1)。 光和年間(西暦178年~184年)、「國皇星」が東南の方角に地面から十二丈(約39メートル…見た目でしょうね)、離れたところにあって、たいまつのような形だったそうで、十日あまりでそれが見えなくなったとのこと。えー、会稽の兵乱のときと同じように、現代の我々には相変わらず、意味不明なんだけど、ちゃんと、占いにあって「國皇星は内乱をもたらす。外と内で兵を失う」とのこと。(ところで「國皇星」って今で言う何の星だろ?) これから先、説明する出来事は、奥が深く、十数回にもわけて説明できそうだけど、それじゃ、本筋の「孫氏からみた三国志」から外れそうなので、関係してくるところや清岡の気に入ったところに茶々を入れながら説明していきたい。 例によって初めは後漢書から。主にその皇甫嵩伝より2)。 冀州の鉅鹿県に張角(字、不明)という人がいて、自らを「大賢良師」と称し、「黄老道」というのをおさめ、弟子を養い、ひざまづき拝礼させて自らの過失をのべさせ懺悔させていた。おふだ、神水、呪文によって病を治し、病人はすこぶるいえ、百姓は信じ、これをしたっていた。 えー、まぁ本当に病が癒えたかどうか今じゃわからないけど、それ以外は新興宗教っぽい感じ。さしずめ、張角は教祖様にあたるんだろうか。 ちなみに後漢書本紀だと張角は「黄天」と称して3)、後漢紀だと「大醫」(大医)と称し4)、三国志魏書の二公孫陶四張伝の注にひく典略によると「太平道」をおさめていたらしい5)。この張角の集団が解説本や小説で出てくるときはなぜか「黄老道」より「太平道」の方がよく使われるので、「太平道」という言葉を覚えておくと良いかも。 それで張角は弟子八人を四方へ送り込み、善道により天下を教化した。弟子をつかって布教活動? なんて風におもえてくる。 そういうことが十年余り続くと、人が数十万人ほど集まり(信者?)、青州、徐州、幽州、冀州、荊州、楊州、  州、豫州の郡や国の間でネットワークができるほどだった。そのまま、三十六方を置いた。「方」(「後漢紀」だと「坊」4))というのは将軍みたいなもので、大きい「方」(→「大方」)は一万人余り、小さい「方」(→「小方」)は六、七千人、居て、それぞれ渠帥(指導者みたいなもの?)がいた。 州、豫州の郡や国の間でネットワークができるほどだった。そのまま、三十六方を置いた。「方」(「後漢紀」だと「坊」4))というのは将軍みたいなもので、大きい「方」(→「大方」)は一万人余り、小さい「方」(→「小方」)は六、七千人、居て、それぞれ渠帥(指導者みたいなもの?)がいた。 |

|
|
▲参考:譚其驤(主編)「中國歴史地圖集 第二冊秦・西漢・東漢時期」(中國地圖出版社出版)
張角をリーダーとするその集団はちゃんと宣伝活動(?)をしていたみたいで、「蒼色の天は(蒼天)すでに死んだ 黄色の天(黄天)はまさに立つ その年は甲子にある 天下は大いに幸せとなる」なんてデマをとばしていた。よくわからない内容だけど、先のあげた文を見ると、(黄天)とは張角の制度かなにかだろうか? とにかく、「甲子」の年に何かあるぞってことはわかりやすかった6)。もっとわかりやすくしたかったのか、さらに白い土(石灰かなにか?)で京城(みやこ)の寺門(てらかやくしょの門、どっちだろ)や州や郡の官府(やくしょ)に「甲子」と書いたとのこと。(その光景を想像すると、「誰や、こんなとこに落書きしたのは!」とか言って、すぐ消されそう・笑)で、「甲子」の年とは光和七年(西暦184年)のこと。 その年に、「大方」の一人がまず荊州と楊州で数万人、集めた。その「大方」の名前は馬元義。馬元義は待ち合わせをし、  というところから出発することにしていた。数万人も集めて、何かの運動?(今で言うフラッシュ・モブ?)なんて、疑問に思ってしまうけど、実は全然、違う。答えは次第にわかってくる。 というところから出発することにしていた。数万人も集めて、何かの運動?(今で言うフラッシュ・モブ?)なんて、疑問に思ってしまうけど、実は全然、違う。答えは次第にわかってくる。馬元義は京師(みやこ)へ数回、行って、中常侍(宦官の役職)の封  や徐奉たちと内応していた。その内容は何かというと、三月五日に外と内から一斉に反乱を起こそうという約束。つまり、外からは馬元義が集めた数万人で京師(地名でいう、 や徐奉たちと内応していた。その内容は何かというと、三月五日に外と内から一斉に反乱を起こそうという約束。つまり、外からは馬元義が集めた数万人で京師(地名でいう、 陽のこと)を攻め、内からは封 陽のこと)を攻め、内からは封 や徐奉などが反乱を起こすって手はず。 や徐奉などが反乱を起こすって手はず。そう、戦乱が起ころうとしていたのだ。 ところが三月五日を迎える前に、張角サイドに裏切り者が出る。張角の弟子、濟南國(「後漢紀」だと「濟陰」4))出身の唐周という人。唐周は馬元義のことを上書(皇帝や朝廷にお手紙)して告発する。そのため、京師で馬元義は捕らえられ、車裂きの刑にあう(大規模な戦乱を起こそうとするんだから、さすがに過激な刑)。 (2003年11月22日追記)後漢紀だと、五月乙卯(七日)付けに「馬元義たちが京都で謀反を起こし、処刑された」とのこと。この日付が謀反を起こした日なのか、処刑された日なのか不明。ただ、前者だったら、ここで書いている話の流れにはならない。まぁ、それはそれでいいかな7)。 |
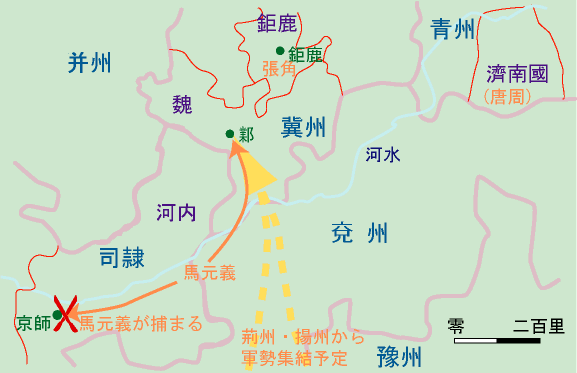
|
|
▲参考:譚其驤(主編)「中國歴史地圖集 第二冊秦・西漢・東漢時期」(中國地圖出版社出版) 但し、画面上のルートの位置に根拠はありません
馬元義は処刑されたんだけど、そんな陰謀が明るみにでたもんだから、あわてて皇帝(死後、靈帝と呼ばれる)は三公(太尉、司徒、司空の三つの役職。最高位)や司隸に命令し、 鉤盾令という役職の周斌という人に三府(三公の役所)の属官を率いらせ、宮中の衛兵や禁中の人々が張角を信仰しているかどうか、証拠をあげ調べ、その結果、やっぱり居たみたいで(とばっちりも居る?)、千人あまり、殺された。こんな過激な弾圧をするなんて、かなり危機感があったようで…… さらに、冀州を探り、リーダーの張角たちを追い捕らえようとする。張角たちはそのことを知って昼夜、進み、「方」へ、とある指令をした。 さてその指令とは? というわけで、次回に続く……
1) 天文現象。「光和中、國皇星東南角去地一二丈、如炬火状、十餘日不見。占曰:『國皇星為内亂、外内有兵喪。』其後黄巾賊張角燒州郡、朝廷遣將討平、斬首十餘萬級。」(後漢書志第十二 天文下より)。黄巾にまつわることはあと一つあったんだけど、載せてない。どちらもピンポイントな占いじゃないんで、どちらも載せないでおこうとおもったけど、許昭のとき(>>参照)、出したし、今回も、てなことです。
2) 今回の元ネタ。皇甫嵩伝の黄巾関連。「初、鉅鹿張角自稱『大賢良師』、奉事黄老道、畜養弟子、跪拜首過、符水咒説以療病、病者頗愈、百姓信向之。角因遣弟子八人使於四方、以善道教化天下、轉相誑惑。十餘年閒、衆徒數十萬、連結郡國、自青・徐・幽・冀・荊・楊・  ・豫八州之人、莫不畢應。遂置三十六方。方猶將軍號也。大方萬餘人、小方六七千、各立渠帥。訛言『蒼天已死、黄天當立、歳在甲子、天下大吉』。以白土書京城寺門及州郡官府、皆作『甲子』字。中平元年、大方馬元義等先收荊・楊數萬人、期會發於 ・豫八州之人、莫不畢應。遂置三十六方。方猶將軍號也。大方萬餘人、小方六七千、各立渠帥。訛言『蒼天已死、黄天當立、歳在甲子、天下大吉』。以白土書京城寺門及州郡官府、皆作『甲子』字。中平元年、大方馬元義等先收荊・楊數萬人、期會發於 。元義數往來京師、以中常侍封 。元義數往來京師、以中常侍封 ・徐奉等為内應、約以三月五日内外倶起。未及作亂、而張角弟子濟南唐周上書告之、於是車裂元義於洛陽。靈帝以周章下三公・司隸、使鉤盾令周斌將三府掾屬、案驗宮省直衛及百姓有事角道者、誅殺千餘人、推考冀州、逐捕角等。」(後漢書卷七十一 皇甫嵩朱儁列傳第六十一より)。長いですけど、こんな感じ。 ・徐奉等為内應、約以三月五日内外倶起。未及作亂、而張角弟子濟南唐周上書告之、於是車裂元義於洛陽。靈帝以周章下三公・司隸、使鉤盾令周斌將三府掾屬、案驗宮省直衛及百姓有事角道者、誅殺千餘人、推考冀州、逐捕角等。」(後漢書卷七十一 皇甫嵩朱儁列傳第六十一より)。長いですけど、こんな感じ。
3) 後漢書本紀の黄巾関連。これはネタバレ、含んでる。「中平元年春二月、鉅鹿人張角自稱『黄天』、其部帥有三十六方、皆著黄巾、同日反叛。」(後漢書卷八孝靈帝紀第八より)。ここで中平元年とあるけど、わかりやすくしているのだと思う。実際はまだ改元されてなく光和七年。 |
|
4) 後漢紀の黄巾関連。まぁ、後漢書とだいたい一緒かなぁ。こちらは微妙にネタバレ含んでいる。最後のところ。「初、角弟良、弟寶自稱大醫、事善道、疾病者輒跪拜首過、病者頗愈、轉相誑耀。十餘年間、弟子數十萬人、周遍天下、置三十六坊、各有所主。期三月五日起兵、同時倶發。角弟子濟陰人唐客上書告角、天子遣使者捕角。角等知事已露、因晨夜敕諸坊、促令起兵。」(後漢孝靈皇帝紀中卷第二十四より)
5) 太平道。「熹平中、妖賊大起、三輔有駱曜。光和中、東方有張角、漢中有張脩。駱曜教民緬匿法、角為太平道、脩為五斗米道。太平道者、師持九節杖為符祝、教病人叩頭思過、因以符水飲之、得病或日淺而愈者、則云此人信道、其或不愈、則為不信道。」(三國志卷八魏書八 二公孫陶四張傳第八」の注に引く「典略」より)。別に正史に載っているわけじゃないのに、これほど広まる名称だなんて、よくよく考えてみると驚き。ほんとに張角と張脩は関係があったのかな。 6) (2003年10月11日追記)甲子。日本語の読みで「きのえね」。暦の数え方にある一つ。年や日に使う。甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥という感じで、甲子を筆頭に60個ある。だから、次の60年周期のはじまりだから、世の中が変わるんだって意味があったのかなぁ 7) (2003年11月22日追記)後漢紀の記述。「五月乙卯、黄巾馬元義等於京都謀反、皆伏誅」(後漢孝靈皇帝紀中卷第二十四より) |
| << |