前回、あまり文台(孫堅)が出てないし、まだ黄巾編が終わっていなくて申し訳ないが、話が一気に飛ぶ。
まず文台たち、漢人とは人種が違う、西羌について話が始まる(飛びすぎ?)。
後漢書西羌伝によると1)、西羌の元々の出自は三苗という古代の未開民族とのことで、「姜」の姓から別れたとのこと。すなわち舜(五帝の一人。先史時代の人)の四凶(共工、驩兜、三苗、鯀のこと)2)の流れで三危(地名)の人々であり、その国は南岳(どこ?)の近くにあるそうな。
河關(涼州隴西郡)3)の西南に羌の地があり、賜支(地名)の岸辺から河首と呼ばれるところにいたるまで、綿の地が千里あるそうな。
南に蜀・漢(益州のところ)の砦の外の蠻夷(異民族)と接し、西北に
 善・車師諸國と接している。うんうん漢人から見て辺境という感じ。
善・車師諸國と接している。うんうん漢人から見て辺境という感じ。常に居住しているところはなく、水や草の近くに居住している。五穀を軽んじ(つまり農業をせず)、産牧(牧畜)を生業にしている。そのならわしや氏族は決まってなく、あるいは父の名、母の姓をもって種の呼び名としている。
というような西羌なんだけど、ここから「孫氏からみた三国志」の時代(黄巾の乱の時代)までいろんな西羌の部族(と呼んでいいかわからないけど、いろんなグループ)が歴史にでてくる。そしてそれらのいくつかは漢人と戦いの連続を繰り広げる。勝ったり負けたりくだったり。
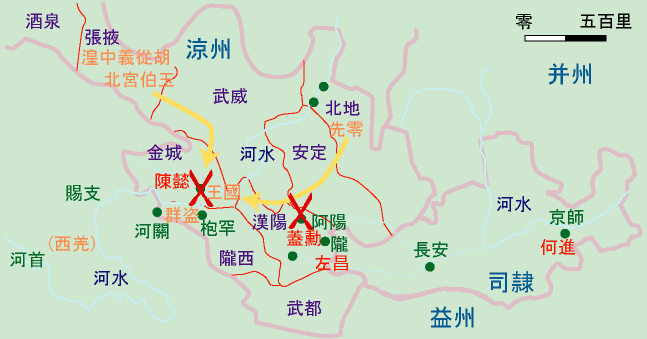
 徴という人を殺す
徴という人を殺す 強弱。被服飲食言語略與羌同、亦以父名母姓為種。其大種有七、勝兵合九千餘人、分在湟中及令居。又數百戸在張掖、號曰義從胡。中平元年、與北宮伯玉等反、殺護羌校尉
強弱。被服飲食言語略與羌同、亦以父名母姓為種。其大種有七、勝兵合九千餘人、分在湟中及令居。又數百戸在張掖、號曰義從胡。中平元年、與北宮伯玉等反、殺護羌校尉